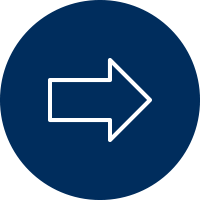中華民国(台湾)
Republic of Chine
☆印付のタイトルは、タイトル部分をクリックすると情報源サイトに移動します。

台湾の教科書に載っている日本人 八田與市氏
1895年、日清戦争で勝利した日本は、国内の食糧不足を補う為に統治国である台湾の農業強化を打ち出しました。
そんな日本が注目したのは香川県ほどの面積をもち、台湾の全耕作地面積の6分の1を占める嘉南平野でした。
しかしそこは雨期には集中豪雨のたびに河水が氾濫し、乾期には干ばつに襲われてしまうという農作物が殆ど育たない不毛の地でした。
60万人にも及ぶ農民達は食べる物にも不自由し、ときには飲み水すら手に入らないなど極貧に喘いでいました。
そこで、日本から土木技師として派遣された八田與一は、烏山頭(うさんとう)地区での大規模ダムの建設を計画します。
しかし、八田の提案したダムは当時世界に類を見ない世界最大規模のダムで、広大な平野に灌漑用水を巡らせようというものでした。
その広さは東京都23区の倍以上にも及び(約1500k㎥)、水路の総延長は1万6千㎞、万里の長城の2.5倍以上になりました。
その為、工事費用は莫大で台湾総督府総予算の3分の1にもなり、現在の金額に換算すると5000億円以上とかつてない規模のプロジェクトでした。
あまりの費用に台湾総督府は難色を示し、工事を縮小するように八田を促します。
八田は「それでは水量が少なく、平野全体に水が行き渡りません」
「一時しのぎではダメです。農民たち全体が豊かにならなければ、造る意味がありません!」
と食い下がります。
当初、金額的にも規模的にもあまりにも大き過ぎて、誰も本当に実現するとは思っていませんでした。
しかし、小さいダムでは水が行き渡らず、住民の格差が生まれてしまうことを懸念した八田は自分の思いを曲げず、計画書を何度も何度も練り直しました。
そして3年後の1920年、粘り強い交渉の末、八田は、費用の半分を現地の農民達も担うことを条件に、ダムの建設許可を勝ち取ったのです。
ところが、費用の半分を負担しなければならないと聞いた地元住民達は猛反対します。
「なぜ我々がお金を負担しなくてはいけないんですか!」
そんな地元住民に八田は「ダムができれば必ず豊かになる。皆さんの子供や孫たちの世代が、安心して暮らせるんです」と必死に説きましたが、地元住民には納得してもらえませんでした。
そして、地元住民の理解が得られず問題を抱えたまま、何年続くか分からないダム建設がスタートしました。
日本人・台湾人合わせて約2000人が、険しい山奥での力仕事に従事しました。
しかし、衛生状態も悪く、労働環境はまさに最悪でした。
そこで八田は”家族が側にいれば、働く上での励みになる”と作業員が家族と住める宿舎を工事現場近くに造りました。
そこには、学校や病院などの公共施設や、映画館やテニスコートなどの娯楽場も造られました。
集会所に集まってゲームをしたり、定期的にお祭りを開いたり、作業員達はここでの生活を心から楽しむことができました。
当時の台湾では、台湾人に対して扱いをぞんざいにするなど差別意識を持つ日本人もいましたが、八田にはそんな意識が全くありませんでした。
台湾の作業員達とも家族のように接し、上からではなく、同じ目線で仕事をする八田の姿勢に心を打たれた台湾の人たちは次第に八田に心を開いていきました。
マラリアが蔓延した時には、八田は当時極めて高価だった特効薬「キニーネ」を日本から大量に購入し作業員達に与えたこともありました。
地元の反対も弱まり、全てが上手く行くように思われました。
しかし着工から2年たったある日、トンネル工事の最中に石油ガスによる爆発事故が発生。
死亡者50人以上、負傷者100人以上の大事故でした。
八田は犠牲者の遺族のお見舞いに奔走しました。
工事が続けられるかどうか危ぶまれましたが、台湾の人たちは、
「八田與一は俺達のおやじのようなものだ。俺達の為に、台湾の為に、命がけで働いているおやじがいるんだ。おれたちだってへこたれるものか。」と、逆に八田を励ましました。
1923年、日本では関東大震災が発生し、その被害の大きさに台湾総督府も年間予算の30%を復興支援の財政援助として申し出ました。
その結果、ダムの工事費用は大幅に削られ、八田は台湾総督府から作業員の半数を解雇するように言い渡されました。
”自分達から首を切られるのでは?”と心配する台湾作業員達の不安をよそに、八田は日本人から解雇していきました。
台湾人作業員達は驚き、なぜ自分たちを優遇して残したのか、その理由を尋ねると、八田はこう答えました。
「当然ですよ。将来このダムを使うのは君たちなんですから」
日本人は日本でも仕事ができる。
台湾人はこの地でずっと生きていく。
自分たちのダムは自分たちで造ってほしい。
というのが八田の思いでした。
作業員達は、八田を心から信頼するようになったのです。
また、八田は解雇者の再就職先を探す為にあらゆるつてを辿り奔走しました。
見つけた斡旋先に、工事が再開されれば優先して再雇用するという条件をつけたそうです。
八田は工事が終わりに近づいた1930年3月、工事のために 亡くなった人々とその遺族ら134人の名前を刻んだ「殉工 碑」を建てました。
そこには、工事で亡くなった全員の名前が日本人・台湾人の区別なく亡くなった順に刻まれています。
数々の危機を乗り越え1930年、10年の歳月を経て、貯水量1億5千万tを誇る当時東洋一大きい烏山頭ダムが完成しました。
灌漑用水が隅々に行きわたるまでには、実に丸2日かかったそうです。
そうして不毛の地と言われた嘉南平野は、米・サトウキビなどが豊富に獲れる、台湾一の穀倉地帯へと生まれ変わったのです。
水田は30倍に増加し、ダム完成から7年後の1937年には生産額は工事前の11倍に達し、サトウキビ類は4倍となりました。
台湾の人達は、ダムを見渡す丘に 八田の銅像を建てましたが、戦争末期の金属類供出が呼びかけられた頃、忽然と姿を消してしまいました。
実は地元の方によって、近くの駅の倉庫に隠されていたのです。
戦後、国民党政府が日本統治時代の痕跡を抹殺することに躍起になっていた間も隠し続けました。
蒋介石政権のも とで、日本人の銅像を隠し持っていることは非常に危険でしたが、銅像は台湾人によってひたすら守られました。
そして、蒋経国の時代となり、ようやく表に出されもとあった場所に設置されました。
(2016.1)

台湾のレシートには、くじになっている?!
台湾のレシートには、くじが付いています。
これは政府が小売店の脱税対策に行っており、レシートの上部に8桁の番号が記載されておりますが、その番号がくじになっているのです。
2か月に1度当選番号が発表され、運が良ければ特奨NT$200万が当たります。
特奨:NT$200万
二奨:NT$4万(特・頭奨と下7桁が同じ)
三奨:NT$1万(同下6桁)
四奨:NT$4千(同下5桁)
五奨:NT$1千(同下4桁)
六奨:NT$200(同下3桁)
運良く当たったら、郵便局の貯金業務窓口で換金できます。
三奨以上は市・県の指定郵便局での取り扱いとなります。
レシートの裏面の欄に、
・窓口に来た人の名前
・当選者の名前
・身分証明書番号
・当選者の住所
を書き込みます。
窓口で、その当選レシートと身分証を見せたら、換金してもらえます。
≪当選番号発表日≫
1〜2月のレシート
3/25発表➡4/6~7/5換金
3〜4月のレシート
5/25発表➡6/6〜9/5換金
5〜6月のレシート
7/25発表➡8/6〜11/5換金
7〜8月のレシート
9/25発表➡10/6〜1/5換金
9〜10月のレシート
11/25発表➡12/6〜3/5換金
11〜12月のレシート
1/25発表➡2/6〜5/5換金
(2016.1)

食事は外で済ませる
台湾では、普段の食事も外食で済ませるのが一般的です。
一食の価格は、だいたい50〜100元程。
台湾では外食の料金がそれほど高くないので、自炊してもそれほど節約にはならないこともあり、毎日自炊する習慣があまりありません。
また、台湾では時間帯によって営業している店が違うので、食事の時間帯に合わせて出かける食堂も変わります。
(2016.1)

台湾の女子トイレの驚き
台湾の女性用のトイレでは、便座が汚れていることがあります。
年配の人が洋式トイレを和式風に使用しているからです。
つまり、便器に腰掛けず、その上に乗ってしゃがんで用を足しているのです。
公衆トイレでよくあるようなので、デパートなどのトイレを利用したり、クリーナーを持参すると便利です。
また、台湾では「女子トイレに男が入ったの!?」と思えることも度々あります。
女子トイレなのに便座が上がっていることがあるからです。
日本では、男性が入った後に見られる光景の為、女子トイレでは有り得ません。
実はこれ、台湾女性が親切心で行っている行為で、「綺麗にしましたよ」という意味があるそうです。
(2016.1)

台湾流結婚式
台湾の結婚式には、日本人にとって不思議に映る面白い習慣がいっぱいです。
そんな台湾流の結婚式の不思議情報をいくつかご紹介します。
式は2回?!
最近はまとめて1度に済ませるカップルも多くなっていますが、台湾の伝統では、婚約式、結婚式と2回の式を挙げます。
婚約式は新婦の両親がプロデュースし、 結婚式は新郎の両親がプロデュースします。
5月20日は入籍ラッシュ?!
台湾では5月20日、多くの新婚さんが入籍します。
それは5月20日の数字の並びである”520”の発音が「我愛你(私はあなたを愛しています)」と聞こえるからです。
毎年、縁起のよい語呂にあやかった新婚さんが入籍に殺到するのです。
ご祝儀
台湾の結婚式でご祝儀を用意するときは、「紅包(ほんばお)」という赤い封筒を用意します。
日本のような白色で無地の封筒は葬式をイメージさせるものなので、台湾では絶対にタブーです。
台湾では偶数がおめでたい時に用いられ、ご祝儀の金額は偶数が基本です。
ただし、偶数でも「4」は日本と同様「死」と同じ発音の為、避けなければなりません。
ご祝儀の金額は、2200元、6600元、8800元が一般的ですが、自分と相手の関係の深さによりその金額を決めます。
・同年代の友人➡2200元
・部下➡6600元
・特別に親密な関係➡8800元
ご祝儀のお札は、新券でなくても構いません。
式参列の服装
出席の服装は、ポロシャツにジーンズなどラフな格好でも許されます。
ただし、男子は白いネクタイがタブーとなります。
白いネクタイが葬式を連想させるからだそうです。
台湾流指輪の交換
指輪を相手につけてもらうときに、新郎も新婦も第二関節で指を折りまげて、根元まで入れさせないようにします。
そして、自分でしっかり最後まで入れるようにします。
これは、指輪を指の根元まで入れられると、その人の尻に引かれると言われているからです。
尻に引かれないようにする為には、最初が肝心なんですね。
披露宴では、新郎家族は最後までいてはいけない
式中に魚料理が出たら、新郎家族は食べずに退席しなければなりません。
魚を食べないのは、魚と餘(余るの意味)の発音が同じだからです。
新郎側がこうすることによって、新婦側は安心して娘を送り出すことができるそうです。
新郎親族は挨拶せずにそっと立ち去る
新郎側は挨拶もせずにそっと退出し、 新婦側も気づかない振りをします。
そのまま何事もなかったように、食事を続けなければいけないのです。
立ち去るときの挨拶「再見」が「再び婚約をする」という意味がある為、さよなら(再見)を言わないようにする為です。
(2016.1)

台湾流お葬式
台湾のお葬式は、「お祭りか?!」と勘違いするほど賑やかです。
棺をお墓へ運ぶ行列は、まるでパレードのようです。
爆竹を鳴らし、派手な装飾を施したトラックの上でラッパや太鼓が演奏され、その後に参列者が延々と続きます。
こんな風に葬儀を盛大に行うのには、故人の功績を称える意味合いと、葬儀を営む故人の子孫が親孝行であることを誇示する意味合いがあると言われています。
また、”最期は故人のやりたかったことをさせてやろう”という思いやりもあり、おじいちゃんの葬儀にはミニスカートのお姉さん達のブラスバンドやストリップショーを呼ぶこともあります。
このような賑やかな葬儀は、台湾中南部で見受けられるそうです。
一方、近年、台北などの都市部では盛大な葬儀はなりを潜め、葬式業者か運営している「殯儀館」と呼ばれる葬儀場でひっそり行うのが一般的になりつつあるようです。
日本同様、台湾でも伝統的な行事が簡略化してきていますが、お葬式も例外ではないようです。
泣き女
台湾での葬式には「哭葬女」(泣き女)を呼ぶことがあります。
彼女たちは葬儀の時に、遺族の代わりに激しく泣くことによって、悲しさ・辛さ・寂しさを表現します。
れっきと認知された職業です。
葬儀の服装
黒の礼装や黒のネクタイなど黒である必要はありません。
葬儀の服装に特定の決まり事がないため、ジーンズでも大丈夫です。
ただ、常識で考えて華やかな服装での参列はタブーで、黒やグレーなどのダーク系の地味目の色が好まれます。
お香典
台湾でのお香典の基本的なマナーとして、金額は「奇数」となります。
台湾のお葬式のお香典は、その人とどの程度の関係だったかによって金額が変わります。
・職場関係者の家族に不幸があった場合→1,100元か2,100元
・親族の場合→3,000~5,000元
・知り合い程度の関係→1100元、1300元
・親しい間柄→1500元、1700元、2100元
また、日本と同じく4や9がつく金額は避けます。
地域によっては、5や9という数字を避ける風習もあります。
中国語で「祝福永遠不嫌多,関心只要足夠就好」という言葉があります。
「祝福はどれほど多くてもうれしいが、悲しむ人への思いやりは気持ちが伝われば十分だ」という意味です。
香典の額があまりに多いと親族の負担になりますので、多過ぎず少な過ぎず配慮して入れるのが良いでしょう。
お香典を包む袋は必ず『白包(白い袋)』です。
白包袋は、コンビニエンスストアなどで手軽に購入できます。
台湾のお香典は、故人の宗教や各地域によって形式が異なり確認が必要ですが、白包の中央上に「香奠」と書き、自分の名前は左下部に「○○○○敬輓」と書きます。
埋葬
台北は火葬が主ですが、田舎のほうにいくとまだ土葬を行っているところもあるようです。
(2016.1)
台湾
日本統治時代の
建造物
ダムのほとりには烏山頭水庫公園があり八田與一の銅像と八田與一夫妻のお墓があります。
台湾のどこにも在る大理石でなく、わざわざ日本風の花崗岩を探し造られました。
この銅像の前を通る地元の農民は、今でも誰となく手を合わせて拝んで通っていきます。
毎年5月8日の命日には追悼式が行われ台湾総統までが参拝に訪れています。
1895年より台湾を統治する事になった日本が、行政官庁として早速造ったのが台湾総督府です。
1945年連合国軍の大空襲を受け倒壊や火災により、ほぼ全面的に使用不可能となりましたが、1947年から修復工事が始まり翌年には再度使用し始め、それ以降は何回か修復を繰り返すも、ほぼ原型通りの姿で現在に至っています。