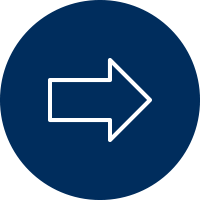フィンランド
Republic of Finland
☆印付のタイトルは、タイトル部分をクリックすると情報源サイトに移動します。
フィンランドで一般的な名字といえば、コルホネン、ヴィルタネン、ニエミネンなどなど。
名字終わりに「~ネン」とついていたら、ほぼフィンランド人と思って間違いないです。
フィンランド人の1/3以上が「nen(ネン)」で終わる姓をもっています。
フィンランド語で「ネン」は通常「小さい」を意味しますが、名字に使うと一族が住んでいた場所を表すことが多くあります。
ヴィルタネンの意味はもともと「小さな沢」ですが、名字では一族が沢の近くに住んでいたこと示します。
マキネンも本来「小さな丘」を意味しますが、名字では一族が丘からやって来たことを表します。
(フィンランド大使館)
妊娠6か月に入ると、フィンランドの妊婦さんは国からプレゼントを受け取ります。
それは育児スターターキット「アイティウスパッカウス」です。
中には、スノースーツ、帽子、手袋、防寒用のボディスーツ。
さすが雪国、防寒グッズがしっかり入っています。
寝袋とシーツ。
赤ちゃんの衛生用品、帽子、目出し帽、靴下、タイツ、絵本、おもちゃ。
バスタオル、温度計、ヘアブラシ、歯ブラシ、爪切り、食事用エプロン、スタイ(よだれかけ)、ガーゼ、紙オムツと、衛生用品も細々したものまで揃っています。
産褥パッド、母乳パッド、コンドーム。
ママの体に必要なもの、家族計画に必要なものまで網羅され、至れり尽くせりのラインナップです。
布おむつ、ベビー服は男女問わず着せられるものが入っているので、性別が判明していない場合でも安心です。
生後すぐに着るものから1歳頃に着るものまで、サイズも豊富に入っています。
そして、箱の底はマットレスになっているので、ベビーベッドとして使えるのです。
成長した暁には、おもちゃや子どものグッズを収納することも出来ます。
これらは国から送られてくるものなので全て無料です!!
妊婦さんは「アイティウスパッカウス」か、現金140ユーロのいずれかを選んで受け取ることが出来ますが、現金を貰うより遥かに価値がある内容の為、95%もの妊婦さんが「アイティウスパッカウス」を選んでいるそうです。
さらに、フィンランド国籍を持ちながら海外に居住している人も、申請すれば販売してくれるそうです。
「フィンランド国籍じゃないけど欲しい…」という方にも朗報です!
実は一般販売もしていて、ムーミン仕様のものも販売されています。
(2015.12)
フィンランドでは「産休」が105日、両親のどちらが取得してもよい「育児休暇」が158日、合わせて263日の「産休・育児休暇」があります。
これらの休暇中は、所得の約66%が保障されています。
「産休・育児休暇」後の264日以降は無給になりますが、子供が3歳になるまで職を失わずに休暇を延長することが出来ます。
その間は自分で保育するので「家庭育児手当」を受けることができます。
基本手当は月額294.28ユーロ(約3万8,600円)、これに「養育手当」も並行して受け取ることが出来ます。
「養育手当」は子供が17歳になるまで支給され、第一子では100ユーロ
(約13,100円)、第二子では110.50ユーロ(約14,500円)というように、子供の数に応じて支給額が増えます。
このほか父親には「父親休暇」があり、6日~30日までの休暇をとることが出来、父親も新生児のお世話に精を出します。
フィンランドのリッポネン元首相が在任中に父親休暇をとり、当時の英国のブレア首相もそれに倣って休暇を取得したのは有名な話です。
(2015.12)
経済協力開発機構が実施している学力到達度調査において、フィンランドは常に世界トップクラスの実力を保持しています。
その為、フィンランドの教育制度は近年、世界各国の教育機関から注目を集めています。
これは時間をかけ国が行ってきた平等の教育政策によるものです。
フィンランドでは自国の国籍をもつ子供だけでなく、難民や移民といったフィンランドに暮らす外国人の子供達も平等に教育を受ける権利が保障されています。
フィンランドの義務教育は日本と同じ6・3制で、7歳から小学校に入学します。
中学卒業後は、普通高校と職業訓練校に別れ、中学卒業者の約6割が普通校、約4割が職業訓練校へ進学します。
高校受験は、9年生の前期までの通知表の成績の平均点によって合否が決まります。
この成績も学校での定期的なペーパーテストだけでなく、日々の学習の取り組みや成果なども点数化されるため、日本のような進学塾や予備校は存在しません。
高校側は成績の良い生徒から順番に入学させる為、生徒は一度に5校まで出願することが出来ます。
大学受験は、まず3年の春に実施される高卒認定試験を受けて合格した上で、志望する大学の入学試験を受験し、合格すれば大学へ進学出来ます。
学費は就業前教育から義務教育、高等学校、大学まで全てが無償。
義務教育の期間は教科書、鉛筆、ノートなどの文房具から給食費も無償となっています。
高校では学費、給食費は無料ですが、それ以外の教材は自己負担となり、
大学では教材費と一食あたり2ユーロ程度の給食費が自己負担となります。
(2015.12 世界と日本の教育)